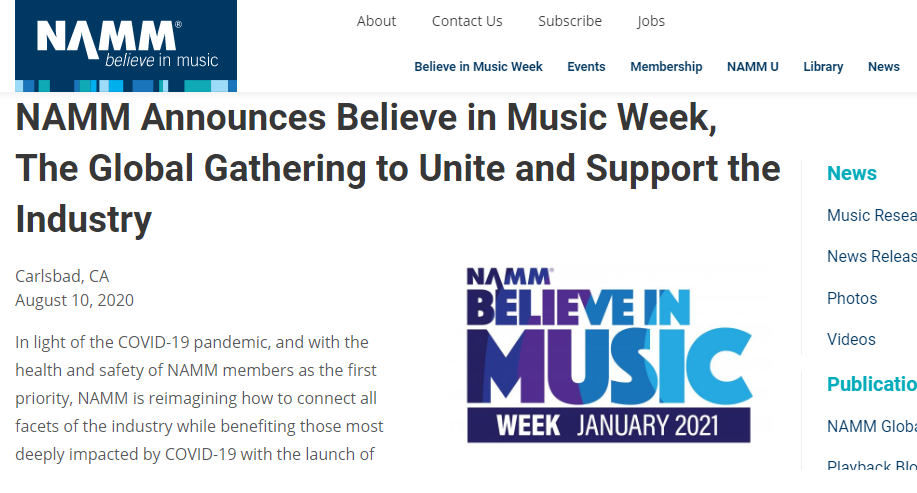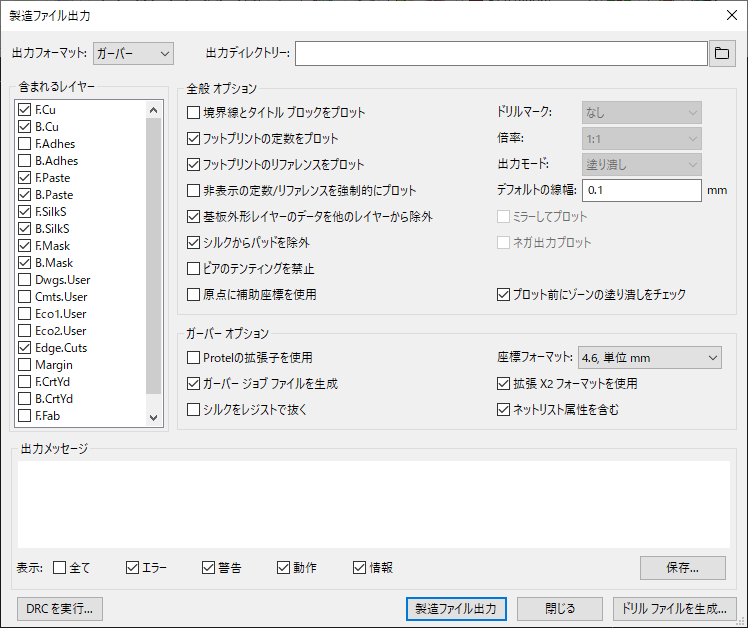今年MIDI 規格が 38年ぶりに更新され、MIDI 2.0 規格が発表されたというので、話題になりました。
規格書は AMEI のページで閲覧できますので、規格書を斜め読みしただけの知識で MIDI 2.0 を解説してみます。
基本的に MIDI 1.0 を基にして構築されているので、MIDI 1.0 を理解している事が前提になります。MIDI 1.0 は元々31.25kbpsのシリアル片方向の通信でした。MIDI2.0では双方向通信が基本で物理層については言及されていません。無理をすればDIN5Pinのケーブル2本で双方向接続という事もできなくはないですが、実用的には USB接続やBLE接続が基本になると思われます。
MIDI1.0について出てきた問題点:
– 速度が足りない。31.25kbosのケーブル接続ではデータ量が増えてくると機器間のレイテンシーが無視できなくなってきます。USB接続では速度が問題になる事はなくなりましたが。
– データの解像度が足りない。ベロシティやコントロールチェンジの数値はMIDI1.0では基本的に128段階しかありません。これは特にピアノ系楽器のベロシティに対しては不満が多く、MIDI1.0でもVerocity Prefix 等の拡張機能で無理やり解決する手法を取る機器もありました。
– 一方通行なので、相手に届いたかどうかはわからない。なので相互にネゴシエーションを行う事もできません。
という事で個別の問題に対しては割と力技な拡張などで解決を図ったりはしていたのですが、これらをまとめて解決しようとしているのが MIDI 2.0になります。
MIDI-CI
MIDI-CIは双方向通信を使ってネゴシエーションを行うための規格です。ネゴシエーションの対象としては
1. プロトコル (MIDI 1.0 または MIDI 2.0)
2. プロファイル (楽器のカテゴリ等に従って自動設定等を行う)
3. プロパティ (音色の一覧やパラメータの一覧を交換する)
があります。
下位互換を保証するために、このMIDI-CIで使用するメッセージはMIDI1.0でのユニバーサル・システム・エクスクルーシブ内に定義されています。ユニバーサル・システム・エクスクルーシブはメーカー/機種毎の独自機能のためのシステム・エクスクルーシブ・メッセージの中でもマスターボリュームやマスターチューニング等のメーカー間で共通化可能な部分について定義されているというなかなか入り組んだスタンスのメッセージですが、ここに新たなメッセージを定義する事で今までのMIDI1.0機器では単に無視され、MIDI2.0対応機器だけが応答を返すという仕組みができます。