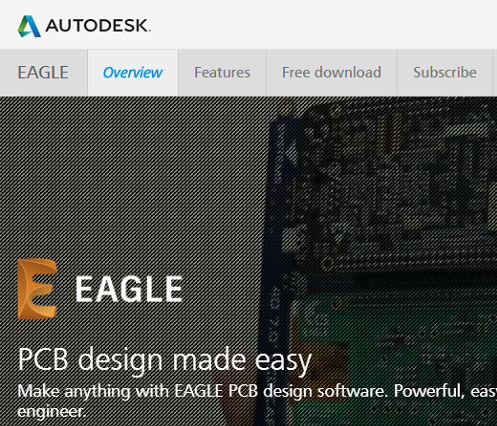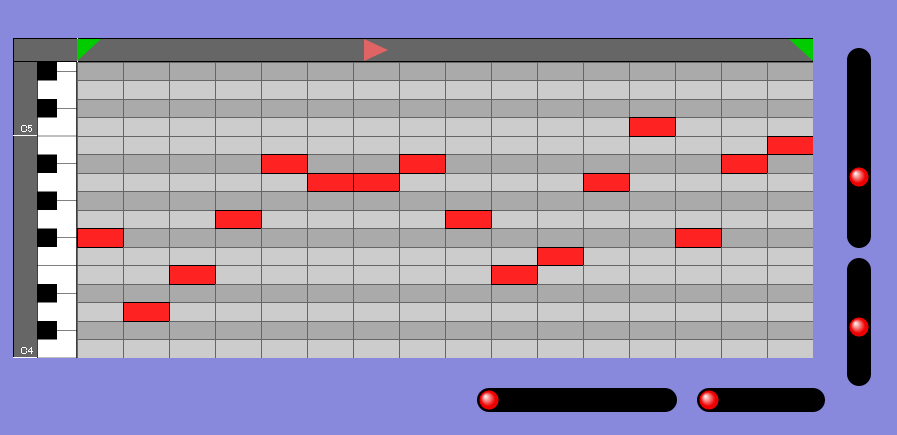AV watchでインタビューが紹介されていた例のUSBに繋ぐ奴の話、危険な感じの話題にかなり突っ込んでいて興味深いですね。
PCのUSBに挿すだけで高音質に? パイオニア「DRESSING」の仕組みを聞いた
個人的にはいわゆるピュアオーディオの世界には特に興味はないのだけど、オカルト的な話が出てくるたびに単に「プラセボ」の一言で終わらせると言うのも堂々巡りで話が進まないし良くないんじゃないかなあとも思うのですよ。あえて結論を出さないという事なのかも知れませんが。
音の良し悪しについて、ピュアオーディオ的には結局の所人間が聴いてどう感じるかが最終的な評価基準になっているのに、計測技術としては頑張っても物理現象としての耳に入ってくる音波の所までしかない、というのが色んな乖離の原因ですよね。耳に入った音が精神作用を及ぼすまでの段階で行われているあやふやな処理の向こう側にしか評価基準がないのでは、こういう奴やらケーブルの違いやらを論じるには心許なさすぎるんじゃないですかね。
良い音がするオーディオシステムを組む事が目的なら、システムの出力を測定して評価基準にすれば良いし、良い音だと感じる事が目的ならブラインドテストで統計的に有意な差が出るかどうかだけが今のところ信頼に足る唯一の評価方法だと思うけど、それは多分わかってやってるんだろうな。
逆に言えば最終的な評価基準を人間が聴いてどう感じるかという所に明確に設定するのであれば、明らかなプラセボだったとしても、意味がないどころではなく非常に有効な事もあるだろうね。ただそれを当然の事のように流布されるような事態になるのは嬉しくない。
いっそ開き直って、良い音で聴くためにはその音楽を聴くための最適な精神状態の準備が必要という観点を入れるというのはどうですかね。
DTMでミックスとかやってる人なら、同じ曲を飽きるくらい何度も聴きながら細かい部分のチューニングに没頭してたのに、いじってる内に全体のバランスがひどい事になってるのにまるで気が付かなかったなんて事もよくあるでしょ。徹夜でミックスして凄く良い音になったような気がして一晩寝てから聴くと思ってたのと全然違うとかありがちだし。
おそらくだけど激しいロックを聴くならハイテンションになってる方が頭に入ってくるし、静かなクラシックを聴くならそれに相応しいリラックスした気分とかあるんじゃないの? ラグジュアリーな部屋を作ったり贅沢な食事をするというのはそういう意味では良い音を聞くための必要な投資になり得るんじゃないですか。
危ない方向に行きそうだけど、音が良くなる飲み薬とかは作れるんじゃないかな。あーそういえばサイケデリック系の音楽ってのが元々そういう方向だったのか。